「ふつうの軽音部」という青春バンド漫画の中で、突如鳴り響いたa flood of circle(フラッド)の音。それは、ただのBGMでも、気まぐれな選曲でもなかった。
この“実在するロックバンド”の登場によって、物語の空気は確かに変わった。
バンドという人間関係の中で、音楽が何をもたらすのか──。この記事では、フラッドの楽曲が作品にもたらした変化と、そこに込められた“感情の揺らぎ”を深掘りしていく。
「ふつうの軽音部」におけるフラッドの登場意義とは?
『ふつうの軽音部』におけるa flood of circle(以下、フラッド)の登場は、単なる“楽曲コラボ”に留まらない重みを持っている。
漫画内で実在バンドの楽曲を取り上げることには、物語の温度やテンポを“現実に接続させる”という大きな仕掛けがある。
そして、その選択が「なぜフラッドだったのか」という問いを生む。この問いの背景には、鳩野ちひろというキャラクターの内面と、バンドという場所における“音楽の役割”が深く関わっている。
バンド名としての“フラッド”が持つ意味
フラッドは、2006年結成の日本のロックバンドで、ボーカル・ギターの佐々木亮介を中心に、HISAYO(Ba)、渡邊一丘(Dr)などが在籍。ブルースやガレージロックをルーツに、熱量の高いサウンドと飾らないリリックで、ライブハウスシーンを中心に根強い支持を受けてきた。
彼らの名前である「a flood of circle」は直訳すれば“円の洪水”──秩序(circle)と混沌(flood)が交錯するような印象を与える。
これは、「軽音部」というある種の“均衡と共存”の場に、彼らの楽曲が投げ込まれること自体が、強烈な異物感として作用する伏線になっていたのかもしれない。
“理由なき反抗”が鳩野ちひろの叫びになるまで
作中で鳩野が演奏するのは、フラッドの代表曲のひとつ「理由なき反抗(The Rebel Age)」だ。
これはただの“勢いのある曲”ではない。理由をうまく言葉にできない感情、それでも溢れ出てしまうエネルギーを音にしているような楽曲だ。
「“反抗”って、かっこいいけど、本当はちょっと怖い」という気持ち。自分の感情を正当化できないまま、それでも演奏するという選択をしたちひろの心が、まさにこの曲に乗って響く。
彼女がこの曲を選んだのは、物語上の「演出」ではなく、彼女自身の言葉にならない叫びを、音が翻訳してくれる瞬間だったのだ。
既存の文脈を壊す異物としての登場
『ふつうの軽音部』の空気は、基本的にやさしい。
部室の温度も、人間関係も、どこか“ふつう”の延長にある。でも、そこにフラッドの「理由なき反抗」が流れた瞬間、空気は変わる。
それまでの既存のバンド曲──例えばくるりやスピッツのような「寄り添い系」の音楽とは真逆の方向で、“何かを壊す衝動”を孕んでいる。
この衝動は、物語のバランスを崩す。そして、それが物語を“動かす”原動力になる。
異物は、ただのノイズではない。物語を変えるエンジンだ。
SNSでも話題──「誰?」から「聴いてみたい」へ
このシーンの公開後、X(旧Twitter)では「#ふつうの軽音部」で「この曲って何?」という投稿が相次いだ。
そこから「a flood of circleって、ガチでかっこよくない?」「知らなかったけど聴いてみたらドハマりした」といった反応が続き、漫画→音楽→現実という循環が生まれた。
特に音楽に詳しくない読者が、物語を通じてバンドを知るという流れは、今のZ世代の“感情優先型消費”と相性がいい。
「ストーリーに共鳴してから音を聴く」ことで、フラッドの持つリアルな衝動がより深く刺さっていく。
これは、SNS時代における“フィクションと現実のハイブリッド体験”の象徴と言えるだろう。
フラッドの音が、物語の“空気”を変えた理由
『ふつうの軽音部』は、空気を描く漫画だ。
部室の中に流れる沈黙、気まずさ、遠慮、そして期待。
音が鳴る前の“空気”にこそ、物語の静かな緊張感が詰まっている。
そんな中、a flood of circleの「理由なき反抗」が放たれた瞬間──読者は思ったはずだ。
「この漫画、空気が変わった」って。
以下では、この“空気の変化”がどのように起こったのかを、3つの視点から解き明かしていく。
静から動へ──「空気をぶち壊す」サウンドの効能
フラッドの音は、徹底的に“動”だ。
粗さがあって、どこか荒削りで、だけど妙に胸に残る。
それまで作中に流れていたのは、スピッツやくるりのような、どこか空気に馴染む音楽だった。
でも「理由なき反抗」は、その空気を“破壊”する。
心地よいだけじゃない。痛みもある。雑味もある。でもそれがリアル。
そのサウンドが鳴った瞬間、ちひろの周囲に漂っていた“ふつう”の空気は、明らかに異質なものに変わっていた。
そして読者も、「この漫画は優しいだけじゃない」と直感する。
ちひろとフラッドの音の“共鳴”と“ズレ”
ちひろは、どちらかといえば“静”の人間だ。
周囲の空気を読みすぎる性格。人とぶつかるのが怖くて、言いたいことを飲み込む癖。
そんな彼女が選んだのが、「反抗」という名のついた曲だった。
ここには、読者を惹きつけてやまない“共鳴”と“ズレ”の緊張がある。
この選曲は彼女の本心と一致していたのか、それとも理想像だったのか。
いずれにせよ、ちひろはそのズレを受け入れ、音に身を委ねるという行動を選んだ。
それがまた、キャラクターと音楽の“接点”として美しい。
「あれを演奏する」とはどういう決断か?
この曲を演奏することは、ある意味で宣言だ。
「自分の殻を破るぞ」とか、「今の空気に甘えないぞ」とか、そんな強い決意を表している。
それは、仲間の空気に馴染もうとする“協調”の姿勢ではない。
むしろ、“波風を立てる勇気”だ。
ちひろがこの曲を演奏すると決めたとき、彼女は無自覚のうちに、部の空気そのものを変えることに手を染めた。
だからこそ、この選曲には物語的な重みがある。
音は鳴った。空気は揺れた。そこから物語の重心が、静かにずれていく。
フラッドという“実在”がもたらす物語のリアリティ
a flood of circleという実在バンドを、『ふつうの軽音部』が作中に登場させた意義は大きい。
それはただのタイアップでも、雰囲気作りでもない。
“実在の音”が“フィクションの物語”に入り込むことで、生まれる熱や現実感がある。
この融合は、読者にとって“観る”から“体感する”への転換点にもなった。
ここでは、フラッドのようなリアルバンドが漫画にもたらした3つの“リアリティの層”を考察していく。
リアルな音楽の熱量が、キャラの感情に宿る
CD音源や配信で聴ける楽曲──それを、キャラクターが鳴らす。
読者は、すでに知っている音を、まだ知らないキャラの心と重ねて聴くことになる。
ちひろが選んだ「理由なき反抗」は、まさにそういう曲だった。
言葉にならない“ムカつき”や“不安”や“拗ねた愛情”が、音として形になっている。
そして、そのリアルな“音楽の熱”が、ちひろというキャラクターに新しい血を通わせる。
読者は気づく。「この曲、ちひろの感情そのものだ」と。
実在の曲だからこそ、感情が“再現”ではなく“宿る”。それが、リアルバンド登場の力だ。
さらに、この楽曲を知っていたファンにとっては、“曲の意味が二重になる”体験にもなった。
これはフィクションと現実を行き来する新しい読書感覚だ。
漫画と現実がクロスオーバーする瞬間
作中でちひろが「理由なき反抗」を演奏する。
読者はページを閉じ、Spotifyを開いて、その曲を聴く。
その瞬間、漫画と現実が地続きになる。
フィクションで感じた感情を、現実のスピーカーから流れる音が補強してくれる。
これは、音楽漫画ならではの“読者体験の拡張”だ。
音を“想像する”しかなかった漫画に、現実の音がリンクすることで、体験は二層構造になる。
「紙から音が聞こえる感覚」。このクロスオーバー体験が、Z世代の感受性にジャストフィットした。
しかもそれは、1回限りでは終わらない。
フラッドの曲を聴くたびに、ちひろの顔が思い浮かぶようになる。
これが物語が現実に侵食する現象なのだ。
フラッドのファンにも刺さったシーンの妙
この演出は、『ふつうの軽音部』ファンだけでなく、フラッド側のファンにも刺さった。
「この曲、漫画で使われてるのエモすぎ」「ちひろ、佐々木亮介の魂を受け継いでた」といった声が、SNS上にあふれた。
それは、ただの引用ではなく、曲の“真意”をくみ取って、物語に落とし込んだからこそ起きた共鳴だった。
“ファンの愛を裏切らない描かれ方”──そこにも、リアリティがあった。
漫画という媒体の中に、現実の文化や熱量が正しく翻訳されていたこと。
それは作品へのリスペクトであり、アーティストへの敬意だった。
そしてなにより、音楽を通じて、漫画が「体温を持ったメディア」になるということの証明だった。
“ふつう”の中にある、特別な共鳴
『ふつうの軽音部』は、タイトルに“ふつう”とあるが、その実、“ふつう”の中にある特別な共鳴を描き出す作品である。
a flood of circleのような実在のバンドを物語に取り入れることで、フィクションと現実の境界を曖昧にし、読者に新たな体験を提供している。
主人公・鳩野ちひろの成長や葛藤、そして音楽への情熱が、読者自身の記憶や感情と重なり合い、“自分ごと”として物語を感じさせる。
この作品は、音楽漫画としての新たな地平を切り開いていると言えるだろう。
今後の展開にも期待が高まる。



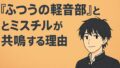
コメント