『ふつうの軽音部』というタイトルを初めて聞いたとき、何を想像しただろう?地味で平凡な部活動漫画──そんな先入観を、あの一話が軽やかに裏切る。鳴らされるのは、誰かの“本音”のような音楽。そしてその中で響くのが、クリープハイプの曲だ。高音で揺れる尾崎世界観の声は、この作品に登場するキャラクターたちの“痛み”に、どこまでも寄り添っていく。
この記事では、『ふつうの軽音部』におけるクリープハイプの楽曲がどのような役割を果たしているのかを追いながら、読者の心に刺さる理由を感情ごとにひもといていく。単なるタイアップではない、“感情の同居”ともいえる関係性が、そこにはある。感情が曲になる。その曲がキャラクターの行動に置き換わる。そんなふうに、物語と音楽が呼吸を合わせる瞬間を追っていく。
『ふつうの軽音部』に登場するクリープハイプの楽曲たち
まずは、物語のなかで印象的に使用されているクリープハイプの楽曲を見ていこう。音楽がただのBGMではなく、「キャラクターの感情の代弁」として鳴らされている点に、この作品の深さがある。選曲ひとつにも、キャラクターの内面が反映される。“この曲を選ぶ人間”が誰かを、読者は音から知る。それが『ふつうの軽音部』における、音楽とキャラクターの密接な関係性なのだ。
「凛と」──藤井彩目がカラオケで選んだ理由
藤井彩目が物語序盤、クラスの空気に飲まれながらもカラオケで選ぶのが、クリープハイプの「凛と」だった。あの場面は、ただの選曲以上の意味をもっている。誰かと盛り上がるための歌ではなく、“自分の存在を確かめるための歌”だったからだ。言葉で「つらい」と言えない彼女にとって、音楽は“痛みの代弁者”だった。
「私、いるよね?」と叫ぶかわりに、あの高音が放たれる。強がりに見せかけた孤独。その裏にあるのは、自分を必要としてくれる“誰か”を無意識に求める、藤井彩目の矛盾した叫びだ。歌詞にある「透明でいたいけど、見つけてほしい」ような感情──それを彩目は歌に託した。そう考えると、あの一曲は“彼女の心の手紙”そのものだったのかもしれない。
「身も蓋もない水槽」──プレイリストににじむ心の揺れ
また、作中では彩目のスマホのプレイリストに、「身も蓋もない水槽」が入っている描写がある。これも見逃せない。彼女がこの曲を選んだという事実は、彼女の“他人の目を気にする癖”と“本音を閉じ込める性格”を浮き彫りにする。水槽の中を泳ぐ魚は、自由に見えて実は閉じ込められている。彩目もまた、“クラスの空気”という名の水槽の中で、自由なようでどこか息苦しい。
この曲の歌詞には、他者との不器用な距離感や、愛情の裏返しとしての冷たさが描かれている。それは、彩目が見せる“ツン”とした態度の裏にある、本当は繋がりたいという渇望と重なっている。誰にも伝わらないかもしれない。それでも曲に頼らなければ、自分を伝える術がない。そんな切実さがにじんでいる。
音楽が“セリフ”になる瞬間──無言で伝わる感情
『ふつうの軽音部』では、会話よりも音楽が感情を伝える手段として描かれることがある。セリフがなくても、誰かの選んだ1曲が、その人の“現在地”を伝える。そのなかでクリープハイプの楽曲は、特に“未整理な感情”を映す鏡として機能している。特に彩目が楽曲を流す場面では、周囲の反応を気にせずに、自分の感情をストレートに表現する契機になっている。
“好き”や“つらい”を言えない人にとって、音楽は“心の翻訳機”になる。『ふつうの軽音部』のキャラクターたちは、クリープハイプを通して、自分の輪郭を確認しているように見える。 そしてその行為こそが、読者の共感を呼び起こしているのだ。言葉よりも真実味のある感情。音楽でしか表現できない感情が、そこにはある。
藤井彩目とクリープハイプ──“声にならない声”を代弁する存在
『ふつうの軽音部』という作品の中で、クリープハイプの楽曲と最も深く結びついているキャラクター──それが藤井彩目だ。彼女の選曲、プレイリスト、歌詞への反応。それらひとつひとつが、“なぜ彼女にとってこのバンドでなければならなかったのか”という問いに直結している。音楽とは、彼女にとって“もうひとりの自分”だったのかもしれない。
言いたいことが言えない。分かってほしいけど言葉にできない。そんな“声にならない声”を、彩目は音楽に託していた。特に、クリープハイプの揺れるような歌声や、あいまいで残酷な歌詞たちは、彼女の複雑な感情にフィットした。“説明できないから、音楽で伝える”。その姿勢こそが、彼女の心の輪郭を示している。
藤井彩目というキャラの“感情構造”
藤井彩目のキャラクターを読み解く鍵は、「言いたいのに言えない」という矛盾だ。気遣いができるのに本音は言えない。人に優しいけれど、自分には厳しい。そして何より、“伝えたい気持ち”があるのに、いつも言葉が追いつかない。そのジレンマこそが、彼女の行動原理になっている。
彼女の感情は、常に“二重構造”でできている。明るく振る舞っていても、心の奥底では誰にも言えない不安や怒りを抱えている。たとえば、にこやかに返事をしながら、内心で不安に押しつぶされていたりする。その“声にならない心の声”が、作品内でクリープハイプによって拾い上げられているのだ。
だからこそ、彩目は音楽に救われた。音に隠して、本音を届けられた。誰かに話すわけでもない、SNSに書くわけでもない、ただ音楽を流して、それが“本当の自分”を代弁してくれる。そんな場面が、誰にでも一度はあるはずだ。
クリープハイプの“言葉にならない歌詞”との共鳴
クリープハイプの歌詞は、“答えを出さない”ことに価値を置いているように見える。「好き」や「嫌い」で完結しない。「わかってよ」とも言わない。その“曖昧な輪郭”こそが、彩目の心とぴたりと重なる。
たとえば、「嫌い」と言いながら、実は「好き」の裏返しだったり、「平気」と笑っていても、「助けて」が奥底で鳴っている──そんな“不器用な本音”を、彼女はいつも胸に抱えている。クリープハイプの曲は、それを肯定してくれる稀有な存在だった。
特に「凛と」や「身も蓋もない水槽」のように、“真っ直ぐじゃない表現”が繰り返される楽曲たちは、彩目の〈言葉にならなかった日々〉に寄り添っていた。彼女にとって音楽は、誰かへのメッセージであり、自分を守るシェルターでもあった。
そしてもうひとつ。彩目は“音楽だけは裏切らない”と、どこかで信じていたのかもしれない。友達も、クラスの空気も、自分自身さえも、揺らいでしまう時がある。でも、音楽は、かければ必ずそこにあって、心の隙間を満たしてくれる。その“揺るがない支え”としての音楽を、彼女はクリープハイプに見出していた。
ファンとしての彼女と、物語の外のリスナーとしての自分
彩目がクリープハイプを“選ぶ”という行為には、キャラクターとしての個性だけでなく、現実にいる誰かと地続きの共感がある。作品を読んでいて、「あ、わかる」と思った瞬間、私たちは“読者”ではなく“共犯者”になる。
彼女のプレイリストに見覚えがある。歌詞の中に、かつての自分の気持ちを見つけたことがある。そんな“痛み”と“気づき”が、読みながら静かに胸を叩く。『ふつうの軽音部』という物語は、登場人物を通して“かつてのあなた自身”と出会わせてくれるのだ。
だからこそ、彩目がクリープハイプを流すだけで、私たちは“あの頃”に引き戻される。そして、ただ音が流れているだけなのに、涙がこぼれそうになる。「そう、私も、そんなふうにしか生きられなかった」──そんな共感が、この作品にはある。
“ふつう”じゃない共鳴──作品と楽曲が重なる理由
『ふつうの軽音部』というタイトルには、ひとつの“裏切り”がある。何気ない日常を描いた部活モノ──そう思って読み始めたはずが、
そこには“痛み”があり、“孤独”があり、“言葉にならない感情”が鳴り響いていた。
そしてその感情に、音で寄り添ってきた存在こそが、クリープハイプだ。
彼らの音楽は、キレイじゃない。むしろ、歪んでいて、尖っていて、時にヒリヒリとした切実さを帯びている。
だが、だからこそ──“ふつう”の顔をしたこの物語に、完璧ではない私たちの人生に、
これほどまでにしっくりくる音はなかった。ここでは、作品と楽曲が共鳴する理由を、感情と構造の両面から掘り下げていく。
“不器用さ”が核心になる構成美
『ふつうの軽音部』の登場人物たちは、みんな少しずつ“うまくやれない”。気を遣いすぎてしまう人。空気を読みすぎて動けない人。
言いたいことを飲み込んでしまう人。──そんな“できなさ”を抱えたまま、それでも音楽をやりたくて、少しずつ一歩を踏み出していく。
その姿勢は、クリープハイプの音楽的スタイルとも深くリンクしている。尾崎世界観の歌声は、まっすぐではない。
声が裏返る。感情に飲まれて、音程さえ崩れる。でも、それが“嘘じゃない”からこそ、胸に迫ってくるのだ。
音楽も、人間関係も、不器用なままでいい。そう言ってくれているようなバンドの音が、
“ふつうでいようとする”ことに疲れたキャラクターたちを、そっと肯定している。
この“ぎこちなさの肯定”こそが、物語と楽曲の接点になっている。
声質と描写──視覚と聴覚のシンクロ
漫画を読みながら、音が聴こえてくる。そんな経験が、誰にでもあるだろうか?
『ふつうの軽音部』には、尾崎世界観の声が“脳内再生”される瞬間がある。
たとえば、藤井彩目のセリフの間合い。カラオケシーンの余韻。無音のコマの“沈黙の温度”──それらがすべて、彼の声に変換されていく。
これは偶然ではない。作者が“音の届く間”を丁寧に描いているからこそ、読者の中にその音が宿るのだ。
「音楽漫画」ではなくても、音が鳴っている。“視覚と聴覚のシンクロ”が、
この作品に独特の没入感を生んでいる。
そしてその“鳴っている音”として、クリープハイプは抜群に相性がいい。
うるさすぎず、静かすぎず、でも痛みの周波数が高い。声質のかすれ。音の重なり方。リズムの不安定さ。
それらがすべて、作品の“感情の断片”と重なってくる。
物語の“痛み”を彩る歌詞の力
『ふつうの軽音部』が読者の心を揺さぶるのは、そこに“語られなかった痛み”が描かれているからだ。
誰にも言えなかった過去。届かなかった思い。伝えたかったのに伝えられなかったこと。
そうした“沈黙の感情”を、この作品は丁寧にすくい上げている。
その痛みに、クリープハイプの歌詞はよく似ている。「言えなかったけど、ずっと思ってた」。
「わかってくれなくていいけど、でも、知っててほしかった」──そんな、
“言葉の隙間”を埋めてくれるようなフレーズが、作品とバンドのあいだに共通して流れている。
このシンクロがあるからこそ、たとえば「凛と」や「寝癖」や「傷つける」が作中で流れると、
読者は“感情”と“音”の両方から揺さぶられる。
文字と音が、言葉と沈黙が、ひとつの“痛み”を描くために重なっていく。
それが『ふつうの軽音部』とクリープハイプの共鳴関係だ。
クリープハイプ最新情報と読後に聴きたいプレイリスト
『ふつうの軽音部』を読んだあと、ただページを閉じるのはもったいない。物語の余韻を、そのまま音楽で引き継ぐ──そんな体験ができるのが、この作品とクリープハイプの共演の強みだ。
ここでは、2024年〜2025年現在の最新動向と合わせて、読後にぜひ聴いてほしいプレイリストを、感情と物語の延長線として提案する。
“音楽が感情を連れてくる”という体験は、読書後にしかできない。言葉が沈んでいった心の深い場所に、今度は音が響いてくる。
フィクションと現実の境目が溶けるような時間を、この音たちと共に味わってほしい。
15周年トリビュートアルバムのリリース情報
クリープハイプは2024年、結成15周年を記念してトリビュートアルバムをリリースした。
くるり、東京スカパラダイスオーケストラ、羊文学、Aimer、リーガルリリーなど、ジャンルも世代も超えたアーティストたちがそれぞれの解釈でカバーを披露している。
このアルバムは、“他人の声で聴くクリープハイプ”という新しい体験でもある。
たとえば、羊文学が歌う「蜂蜜と風呂場」は、原曲とは違う柔らかさをまといながら、やっぱりどこか痛い。彩目だったら、このバージョンをどう感じただろう?と想像したくなる。
読後の余韻をそっと繋げてくれる、優しくて尖った1枚だ。
“あと5秒”で変わる何か──新曲と物語のつながり
2024年後半には、「あと5秒」というタイトルの新曲もリリースされた。
この曲は、何かを言おうとして飲み込んだ“あの5秒”のことを歌っている。好きと言えなかった。泣けなかった。踏み出せなかった──その、たった数秒の中にある“人生の分岐点”。
『ふつうの軽音部』の登場人物たちは、みんなこの“あと5秒”を何度も飲み込んできた人たちだ。
だからこそ、この曲は物語と深く重なってくる。「何も変わらない5秒」だったかもしれない。でも、聴いている私たちの中では何かが変わり始めている。
そんな感覚をくれる1曲だ。
藤井彩目になった気持ちで聴きたい曲5選
最後に、“藤井彩目だったらこの曲を聴いてる”という視点で選んだプレイリストを紹介したい。
これは筆者の完全な主観であり、共感も反論も含めて、読者それぞれの「藤井彩目」を思い描いてもらえたら嬉しい。
- 「凛と」:自分を見失いそうなときに、立ち戻る原点
- 「身も蓋もない水槽」:誰にも言えない息苦しさを抱えて
- 「寝癖」:朝起きたとき、誰にも見せたくない自分のままで
- 「おばけでいいからはやくきて」:どうしようもない夜に、誰かを求めたことがある人へ
- 「一生のお願い」:伝えたかったけど、言えなかったあの気持ち
この5曲は、どれも“彩目のモノローグ”みたいなものだ。
読後、イヤホンを耳に差し込みながら、彼女の心をもう一度なぞる時間を過ごしてみてほしい。
そのときあなた自身の過去や、言えなかった感情にも触れられるかもしれない。
“痛みを抱きしめる音楽”が、物語を刺す理由
『ふつうの軽音部』に登場するクリープハイプの音楽は、どれも“やさしい”わけじゃない。
むしろ聴くたびに心をえぐってくる。それでも、なぜ人はその痛みを求めてしまうのか。
物語における音楽の役割は、雰囲気を演出するためのBGMではない。
それは、登場人物が言えなかったこと、耐えていたことを、代わりに引き受ける“声”になる。
『ふつうの軽音部』の感情の中心には、ずっと言葉にできなかった“痛み”がある。
そしてその痛みこそが、読者の胸に残り続けるのだ。
“痛み”がキャラクターを形づくる
物語を読んでいると、登場人物の感情が“形”になって見えるときがある。
それは笑顔や涙ではなく、「言えなかった言葉」や「踏み出せなかった瞬間」として浮かび上がってくる。
藤井彩目や他のキャラたちは、みな一様に“痛み”を抱えている。
その痛みは、誰かと比べて劣っているとか、過去にトラウマがあるとか、そういうわかりやすさじゃない。
もっと曖昧で、もっと日常的で、でも本人にとっては切実な“うまくいかなさ”だ。
そして、その“うまくいかなさ”をそのまま肯定してくれる存在が、音楽なのだ。
言えなかった後悔も、泣きたくても泣けなかった夜も、声にならないまま終わった感情も。
クリープハイプの音楽は、それらを“記録”してくれる。
“わかってほしくないのに、わかってほしい”
クリープハイプの歌詞に流れるのは、“伝わらなさ”の美学だ。
たとえば、好きとも嫌いとも言わない言葉。優しくもしないけど、突き放しもしない距離。
その中にあるのは、“わかってほしくないのに、わかってほしい”という矛盾だ。
『ふつうの軽音部』のキャラたちもまた、その矛盾の中に生きている。
誰かに心を開きたい。でも、それは同時に傷つくことでもある。
だから彼らは、音楽に託す。言葉じゃなくて、音で伝えようとする。
そのとき鳴っているのが、クリープハイプの、真っ直ぐじゃない音だ。
この“いびつな共感”が、物語と音楽をつなぐ鍵になっている。
読者自身もまた、「誰にも言えなかった」ことがあるからこそ、そこに強く反応する。
物語が終わっても、音は残る
漫画を読み終えたあと、ページを閉じても、キャラたちの感情は消えない。
むしろ、そのときから“読者自身の過去”と結びつき始める。
物語と現実が交差するのは、その“読後の沈黙”の時間なのだ。
その静寂を破るようにして、ふと聴こえてくる音──
それが、クリープハイプの「凛と」や「寝癖」だったら、もう物語は終わっていない。
今度は“あなた自身”が、その音の続きを生きることになる。
音楽は、“もう会えないキャラクターの気持ち”を、そっと引き継ぐメディアだ。
だから物語が終わっても、音は生きている。痛みを抱きしめる音楽こそが、読者にとっての“次の一歩”になる。
“あなたの物語”に、音がそっと寄り添うなら
『ふつうの軽音部』とクリープハイプが交差する瞬間、それは単なるコラボレーション以上の“感情の共鳴”だった。
作品が描くのは、うまく言えなかった言葉や、飲み込んできた感情たち。
そしてそれに寄り添うのが、決して完璧ではない、不器用な音たちだ。
きっと誰しも、ひとつくらい“言えなかったセリフ”があるはずだ。
クリープハイプの音楽は、それを思い出させてくれる。
でもそれは決して責めるようなものではなく、「それでもよかったんだよ」と語りかけるような、どこか温かい痛みだ。
この作品を読み終えたあなたが、もし静かにイヤホンを耳に入れるなら、
その音はもう、藤井彩目や登場人物たちだけのものじゃない。
あなたの過去に、今に、そして明日にまでそっと溶け込んでいく。
物語は、閉じても終わらない。
音がある限り、私たちは何度でも自分の感情に触れ直すことができる。
それこそが、“ふつう”のようで“ふつうじゃない”読後体験の正体だ。


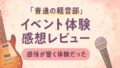

コメント