「上手くなりたい」って、どれだけの勇気を必要とする言葉なんだろう。
『ふつうの軽音部』に登場するあやめは、ギター初心者。だけどその指先には、誰よりも“音を鳴らしたい”という想いが詰まっている。
うまく弾けなくてもいい、でも「好き」を諦めたくない。
この記事では、ふつうの軽音部・あやめの「ギターがうまくなりたい」に宿るリアルな感情を読み解きながら、音楽と成長の物語に共鳴する時間を紡いでいく。
あやめというキャラクターの“ひび割れたリアル”
“音楽漫画”というと、どうしても「才能がある誰か」が主役になることが多い。
けれど、『ふつうの軽音部』は違う。主人公・ちひろのバンドメンバーであるあやめは、ギター初心者で、どこか不器用で、自分に自信がない。
だけど彼女の内側には、誰よりも痛みに近い情熱がある。そしてそれが、読者の胸を打つ。
このブロックでは、“毒舌でクール”とされるあやめの仮面の奥にある、ひび割れた等身大のリアルを掘り下げていく。
中学時代のトラウマが彼女の自己肯定感を蝕んでいた
あやめの過去には、静かでじわじわと心を削っていくいじめがあった。
クラスで無視され、話しかけると空気が張りつめるような空間。そのときの孤独が、彼女の内面に深い傷跡を残す。
「誰かに好かれること」や「自分の意見を言うこと」が、彼女にはリスクにしか思えなかった。
だからこそ、軽音部という“人前で演奏する場”に飛び込むことは、ものすごく大きな決断だったはずだ。
ギターが上手くなること以前に、「やってみたい」と言えたこと。それ自体が、彼女の第一歩だった。
その背景には、“期待されること”すら怖いと感じる繊細さがある。だから、あやめの決意は誰よりも重い。
毒舌とクールさの裏にある“素直すぎる心”
あやめは何かとキツい言い方をする。でもそれは、自分を守るために身につけた鎧。
素直になった瞬間に裏切られる──そんな経験が何度もあったのだろう。
でも、ちひろや桃たちは、あやめのその鎧を無理に剥がさない。
ゆっくりと、少しずつ、彼女が言葉を選べるようになるまで待つ。その関係性の“距離感”が、本作のすごく丁寧なところでもある。
やがてあやめも、小さな「ありがとう」や、ふいに見せる照れ笑いで、「つながっていたい」気持ちを表現し始める。
その一つひとつの変化が、読者にとっては“前進の音”に聞こえる。
あやめがギターを手に取るまでの“選ばなかった道”
軽音部に入っても、あやめは最初からギターをやるとは言わなかった。
「うまくできなかったらどうしよう」「弾けなかったら恥ずかしい」──そんな声が、心のなかで繰り返されていたから。
でも、彼女は少しずつ、音楽に惹かれていく。
バンドの音が重なる感覚、誰かと一緒に“ひとつの音”をつくる楽しさ。
ギターを選んだとき、彼女はようやく「私もやってみたい」と自分の欲を口にした。それは、「もう一度、自分を信じてみたい」という静かな決意だった。
手にしたジャズマスターのネックを握るその手には、選ばなかった道を今からでも歩き出そうとする強さが、確かにあった。
そして、彼女の音が加わったことで、バンドは「ふつう」から少しずつ“特別”になっていく。
あやめはまだ、上手く弾けない。
でもその不完全な音こそが、バンドの“本音”を鳴らしているのかもしれない。
「ギターがうまくなりたい」という叫びの重み
あやめの言葉はいつも控えめで、飾らない。
でも、「ギターがうまくなりたい」という一言には、彼女のすべてが込められている。
うまくなりたい理由を、彼女は多く語らない。
けれど、その音が伝えてくる──誰にも負けないくらいの想いが、確かにそこにあるのだ。
「うまく弾けない」が、なぜこんなに刺さるのか?
漫画の中であやめがギターを弾こうとするシーンは、決して派手ではない。
コードを押さえようとして指が震え、音が出ない場面は、読者にも「あるある」と感じさせる痛みをもっている。
でも、そこには“下手でも向き合っている人間の尊さ”がある。
うまくなりたい。でも、なれない。それでも続けたい。
そんな彼女のもがきは、才能よりも、練習よりも、ずっとまっすぐで、胸を打つ。
読者は気づかないうちに、「自分もそうだった」と共鳴してしまうのだ。
ギター練習シーンに込められた“等身大の焦燥感”
練習してもうまくいかない。
他のメンバーはどんどん上達していくのに、自分だけ取り残される気がする。
そのあやめの表情は、どこにでもいる普通の子の表情だ。
そしてそこが、この作品の感情的なリアリティを支えている。
成長が描かれる漫画は多いが、「成長できないこと」そのものにスポットライトが当たる作品は、そう多くはない。
あやめの焦りや苦しみは、音楽を通じて「なりたい自分になれない」すべての人に通じる叫びでもある。
あやめの音が変わった瞬間──自己肯定感との和解
ある日、ほんの少しだけ、音が鳴るようになる。
それはプロ級の上達じゃないし、誰かに褒められるようなプレイでもない。
でも、その音を聞いた仲間たちは、「いい音だったね」と声をかける。
その瞬間、あやめの目に浮かぶ小さな涙は、「やっと、自分を少しだけ肯定できた」証だった。
ギターがうまくなったこと以上に、「やっていいんだ」と思えることが、彼女にとっての最大の一歩だった。
音を鳴らす。それは、自分の存在を確かめることでもある。
だからこそ、「ギターがうまくなりたい」という言葉は、ただの技術的な欲求じゃない。
それは、“自分を認めたい”という、根源的な願いなのだ。
音楽と向き合う姿が伝える“ふつう”の意味
『ふつうの軽音部』というタイトルは、最初こそ控えめに聞こえるかもしれない。
でも、この作品が描いている“ふつう”は、諦めや平均ではなく、私たちが本当に持っている等身大の輝きだ。
あやめの不器用な姿勢、まっすぐな努力、仲間との関係性。
そのすべてが、“ふつう”という言葉に新しい意味を与えてくれる。
“うまくなる”よりも“やめない”ことの価値
あやめは、どれだけ音がうまく鳴らなくてもギターをやめなかった。
それは、誰かに褒められるためでも、目立つためでもない。
ただ、「音を出したい」「この場所にいたい」──それだけの想いで、彼女は毎日練習を続ける。
続けることは、時に才能よりも難しい。
環境や能力のせいにせず、ただ自分の“好き”と向き合い続けること。
そこにこそ、音楽という行為の、本質があるように思える。
ギター=自己表現としてのあやめ
ギターは単なる楽器ではない。あやめにとって、それは“言葉にならないもの”を伝える手段だ。
うまく話せない想いも、誰かに打ち明けられない寂しさも、指先から音にして放つことで、ようやく外に出せる。
演奏中のあやめは、普段よりも素直で、強くて、脆くて、きれいだ。
そのギターの音は、聴いている側の心の奥にも何かを揺らしてくる。
「誰かの前で弾く」ことは、「自分をさらけ出す」ことでもある。
そして彼女はその“怖さ”と、正面から向き合っている。
あやめとバンドメンバーの関係性が音に与える影響
あやめ一人では、きっとギターを続けられなかったかもしれない。
彼女を見守り、ときに手を貸し、何も言わずそばにいる──ちひろ、桃、厘の存在が、あやめの音を少しずつ変えていく。
最初はぎこちなくてバラバラだった音が、だんだんと“重なる”ようになる瞬間。
そこには、言葉では説明できない「バンドの魔法」が宿っている。
ふつうの音が、ふつうじゃなくなる瞬間。それは、誰かと繋がって初めて鳴る音だ。
「下手でも、進める」──あやめが教えてくれたこと
「うまくなりたい」と願うことは、決して簡単じゃない。
できない自分と向き合うこと、他人と比べてしまうこと、期待されることが怖くなること──そのすべてを引き受けながらも、あやめは、ギターを続けた。
その姿に、私たちは“自分”を重ねてしまう。
なりたい自分にはなれないけれど、今の自分も捨てたくない。
その葛藤を、音で、行動で、静かに鳴らしていくあやめの存在は、「ふつう」という言葉の中にあるいちばん大切な“輝き”を思い出させてくれる。
『ふつうの軽音部』は、音楽を通して“生き方”を描く作品だ。
目立つステージや賞賛よりも、“誰かのために音を鳴らす”ことの喜びや、自己との和解の瞬間を丹念に描くその物語は、静かだけど力強い。
ギターがうまくなる過程以上に、「弾き続けたい」と思える気持ちが、どれほど尊いものかを教えてくれる。
そして何よりも──あやめのように、「下手でも、進める」と思える強さを、私たちは確かに彼女から受け取った。
それは、音楽の話だけじゃない。
勉強でも、仕事でも、恋愛でも、人生そのものでも。
迷いながらでもいい、泣きながらでもいい。
下手でも、自分のままで、ちゃんと前に進める。
あやめのギターがそうだったように、あなたの“音”にも、きっと誰かが耳を傾けてくれている。



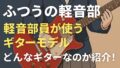
コメント