ギターの弦を弾くように、感情は静かに、でも確かに揺れている。
『ふつうの軽音部』に登場する新田たまきは、そんな“静かな熱”を体現するキャラクターだ。
明るく頼れる副部長として、軽音部を支える彼女。しかし、その笑顔の裏には、音楽に救われ、そして音楽に苦しめられた過去がある。
この記事では、たまきというキャラクターの内面と魅力を、物語の文脈と彼女の音楽的背景を交えて深掘りしていく。
“ふつう”じゃない彼女の生き方が、きっと誰かの心を震わせる。
たまきのプロフィールと音楽との出会い
“軽音部の副部長”という肩書きだけでは、たまきを語り尽くすことはできない。
明るくて頼れる先輩──その第一印象の奥には、音楽と向き合ってきた彼女の“記憶”と“痛み”が折り重なっている。
この章では、たまきのプロフィールからスタートし、音楽に出会った過去、バンド経験、そして“副部長”というポジションが彼女に何をもたらしたのかを丁寧に読み解いていく。
明るさの裏にある“副部長”としての責任感
たまきは谷九高の3年生であり、軽音部の副部長を務めている。
彼女は常に笑顔を絶やさず、後輩たちからも慕われる存在だ。その姿だけを見れば、天真爛漫な“陽キャの先輩”という印象を持つかもしれない。
だが物語が進むにつれ、その笑顔の裏側にある、部を支える責任感と孤独が見えてくる。
特に印象的なのは、新歓ライブのシーン。彼女は周囲に気を配りつつも、自身のパフォーマンスには一切の妥協を許さない。
それは、“背中で引っ張る副部長”としての姿勢であり、メンバーに対して常に自分が支えになろうという意思の現れでもある。
初めてのギターは、好きな人からの贈り物
たまきが音楽に触れたのは中学生の頃。
彼女の初恋の相手であり、家庭教師でもあったひかり先生からギターを譲り受けたことがすべての始まりだった。
たまきにとって、そのギターは単なる楽器ではない。“想いを残した証”であり、触れるたびにその人との記憶が蘇るものだった。
彼女が音楽にのめり込んでいった背景には、愛情と憧れ、そして別れの痛みが重なっている。
ギターを弾くという行為そのものが、たまきにとっては“感情の再生”でもあったのだ。
中学時代からのバンド経験が生んだ“余裕”
彼女は高校入学以前からバンド活動をしていた経験があり、演奏や人間関係に対して独特の“距離感”を持っている。
技術面でも精神面でも、未経験者が多い軽音部の中で、たまきは明らかに安定した存在だ。
その余裕は、過去に積み重ねてきたライブ経験やメンバーとの衝突・協力の歴史から生まれている。
だからこそ、彼女は後輩に対しても過干渉せず、「寄り添いすぎず、離れすぎない」スタンスを貫く。
この“ちょうどいい距離”が、たまきというキャラクターの魅力を作り出しているのかもしれない。
「副部長という肩書き」に囚われない、たまきの“素”
とはいえ、たまき自身は“副部長らしくあらねば”という意識にとらわれてはいない。
あくまで彼女は、自分のスタイルで部を支え、後輩と向き合い、仲間と音楽を作っていく。
だからこそ、時にサボり癖が見えたり、面倒なことを嫌がる姿も描かれる。
その“完璧ではない人間らしさ”が、読者の共感を呼ぶ要素の一つだ。
たまきは、「ちゃんとすること」に疲れた読者にとって、ある種の癒しでもあるのかもしれない。
“部活の中の大人”として、たまきが選んだ距離感
部活という小さな社会の中で、たまきは時に“大人の役割”を担う。
とくに、人間関係がぎくしゃくしそうなとき、彼女はさりげなく空気を読んで場を和らげる。
その一方で、自分の感情をあまり表に出さないという特性もあり、孤独を抱えているように見える瞬間もある。
だが、それでも彼女は他人との“距離”を恐れず、むしろそれを見極めて行動する。
それが、彼女が“音楽”と“人間関係”の中間でずっと悩みながらも進んできた証だ。
過去と葛藤──“ふつう”じゃなかった日々
たまきというキャラクターを語るとき、彼女の“過去”と“葛藤”は決して避けて通れない。
笑顔の裏にあるのは、傷ついた記憶、届かなかった想い、すれ違った友情──そして、それでも音楽を手放さなかった理由。
この章では、たまきが背負ってきた“ふつう”じゃなかった日々に焦点を当てる。
その軌跡は、彼女の弾く音の深さにも、時折見せる沈黙にも、確かに刻まれている。
初恋の先生とギター、そして抑え込んだ想い
たまきの音楽人生は、初恋とともに始まった。
中学時代、彼女は家庭教師だったひかり先生に恋をした。
年上の女性に惹かれたたまきは、当時の自分の感情に戸惑いながらも、強く、でも静かにその想いを抱き続けていた。
やがてひかり先生からギターを譲り受けると、彼女の中で「恋」と「音楽」は一つの記憶として溶け合っていく。
ただ、その恋は決して報われるものではなく、たまきはその感情を誰にも言わず、自分の中に閉じ込めた。
ギターを弾くことは、未だにその想いを手放せていない彼女の、心の延命措置でもあったのだ。
夏帆との“歪な友情”が映す、たまきの不器用さ
高校に入り、たまきは坂口夏帆という友人と出会う。
軽音部の仲間であり、たまきにとって初めて“バンドを組んだ相手”だった。
だが、たまきの人懐っこさや距離の近さは、時に無意識の傷を与える。
夏帆は、たまきに憧れながらも、その曖昧な距離に苦しみ、やがて不登校になってしまう。
たまきは自分が“傷つけていた側”だったことに気づくのが遅く、彼女自身もまた、「人と向き合うことの怖さ」を学ぶことになる。
それ以降のたまきは、以前よりも他人との関係に慎重になるが、それは自己防衛であり、同時に彼女なりの誠実さの現れでもあった。
同性愛者としての描写と、それをどう生きるか
たまきが同性愛者であることが明らかになったのは、第43話だった。
それまでの物語では明示的に語られず、むしろ彼女の恋愛感情は“背景の空気”として慎重に描かれていた。
だが、だからこそ読者の中に残る“感情の余白”が、たまきをより立体的に見せていたともいえる。
彼女自身がそのセクシュアリティに対して声高に主張することはない。ただ、自然体のまま、自分の“好き”を手放さないという姿勢が印象的だ。
たまきは、自分の感情を誰かに押しつけることなく、ただ静かに、でも確かに、“ありのまま”でいることを選んでいる。
“わかってもらえなかった経験”が生んだ沈黙
たまきの過去には、「話しても伝わらなかった」という記憶がある。
それは恋愛でも、友情でも、家庭でも、どこかで彼女は常に“言葉が届かない”壁にぶつかってきた。
だからこそ、彼女は多くを語らない。代わりに、音楽で、演奏で、自分の感情を伝えようとする。
その沈黙は無関心ではなく、むしろ痛みを知っているからこその選択なのだ。
そして、だからこそたまきの演奏は、「言葉より雄弁なもの」として聴く人の胸を打つ。
“ふつう”でいることの難しさと、選んだ道
『ふつうの軽音部』というタイトルが皮肉にも響くほど、たまきの歩みは“ふつう”とは遠い。
恋も友情も、自分の感情さえも、何ひとつ定型的に処理できなかった彼女は、それでも“ふつう”を演じて生きてきた。
だが、音楽だけは、そんな嘘をつかなくてもよかった。
ステージの上で、ギターの前では、たまきは“たまきのまま”でいられたのだ。
彼女がバンドを続ける理由も、部活に身を置く理由も、その一点に尽きるのかもしれない。
音で語るたまき──機材とプレイスタイル
言葉では語れないものを、音にする。
たまきにとってのギターは、単なる楽器ではなく、心を翻訳するツールだった。
彼女の使用する機材やプレイスタイルには、その人柄や過去、そして“今”が滲み出ている。
この章では、たまきの選んだ音、その機材、その響きの意味を追っていく。
音楽でしか伝えられない感情が、確かにそこにはある。
Fender Stratocasterに込めた“想い出”
たまきの愛機は、Fenderのストラトキャスター。
シンプルでありながら表現の幅が広く、使い手によって音の表情が変わるこのギターは、まさにたまきの性格そのものだ。
このギターは中学時代、ひかり先生から譲り受けたものであり、彼女にとって最もパーソナルなアイテムである。
ギターの色や傷跡にさえ、たまきの“歴史”が刻まれている。
弾くたびに想いが蘇るそのギターは、彼女の人生を伴走してきた証だ。
銀杏BOYZを選ぶ理由──感情の爆発としての選曲
軽音部の新歓ライブで、たまきは銀杏BOYZの「あんどんわなだい」を選んだ。
銀杏BOYZの楽曲は、理屈よりも感情でぶつかってくるような衝動性がある。
その一曲を、たまきは全力で叫ぶように歌い上げた。
その姿は、「ふつう」からはみ出すことへの肯定であり、彼女自身の感情の爆発でもあった。
選曲には“叫びたい気持ち”が滲んでいて、それは聴く者の胸にも鋭く突き刺さる。
繊細さと爆発力を併せ持つ演奏スタイル
たまきの演奏は、時に静かで、時に荒々しい。
フレーズの始まりは繊細なのに、サビでは一気に音を爆発させる。
その強弱の波は、まるで感情の起伏そのものであり、「気持ちの揺れ」を音で伝えることに長けている。
テクニックに走りすぎず、感情に寄り添うプレイスタイルは、むしろ“未完成”だからこそ、聴く人の心に残る。
彼女にとって、演奏とは“正確さ”ではなく“届けること”なのだ。
エフェクターと弦にも見える“こだわり”
たまきはBOSSのOD-3(オーバードライブ)を使用しており、その歪みは彼女の歌声と絶妙にマッチしている。
OD-3は“エモーショナルな歪み”を作る定番機材であり、たまきの音色に温かみと鋭さを両立させている。
また、使用弦はD’Addario。テンション感が強く、ピッキングニュアンスが出やすいこの弦は、彼女の“感情を込めた演奏”をより際立たせる。
こうした機材選びにも、“自分の声をどう届けたいか”という意志が反映されている。
“音”にしか残せない感情を抱えて
たまきがギターを持つ理由、それはきっと“声にできない気持ち”があるからだ。
言葉では伝えきれないもの、誰かに話せなかったこと、それらを彼女は音に託している。
その音は、時にメロディとなり、時にノイズとなるが、どれもがたまきの生きてきた証そのものだ。
彼女がステージに立ち、音を鳴らすたびに、誰かの“まだ言えない気持ち”を代弁してくれているようにも感じる。
それこそが、たまきの音楽の本質であり、彼女が“音で語る”ということの意味なのだ。
たまきとは何者だったのか──静けさの中に燃える音
新田たまきという存在は、決して派手でも、強烈でもない。
でも、だからこそ彼女は、多くの読者の“日常”にそっと溶け込んでくる。
誰にも言えなかった想い、距離のとり方がわからなかった友情、“ふつう”に馴染めなかった痛み──そのどれもが、彼女という人物に刻まれていた。
そして、それらを言葉ではなく“音”で語る姿に、私たちは心を奪われる。
ギターを通して伝えられるメッセージは、たまきが背負ってきたものそのものであり、同時に、彼女が誰かに渡したかったものでもある。
『ふつうの軽音部』という作品の中で、たまきはいつも“静かに燃えて”いる。
叫ばずに、でも確かに、自分の想いを音に乗せて生きている。
それは、現実を生きる私たちにも通じる姿勢かもしれない。
“伝える”ことは、何も大きな声を出すことだけじゃない。
たまきが教えてくれるのは、そうした“静かな伝え方”の美しさであり、儚さであり、強さだ。
きっと、彼女が鳴らしたひとつひとつの音は、誰かの胸の中で今も響いている。
それは、あなたの中にも、きっと。


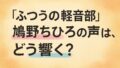
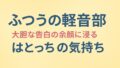
コメント